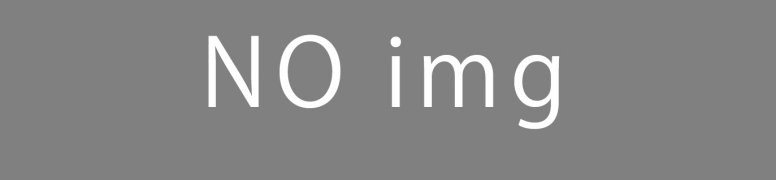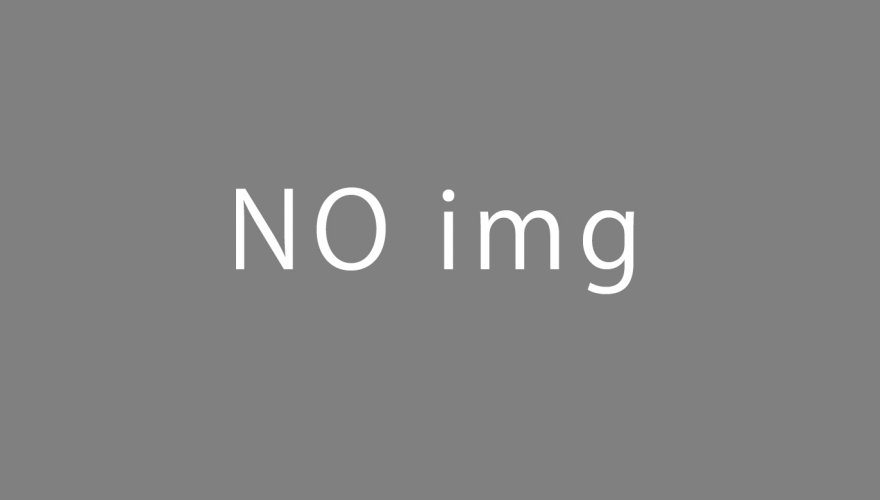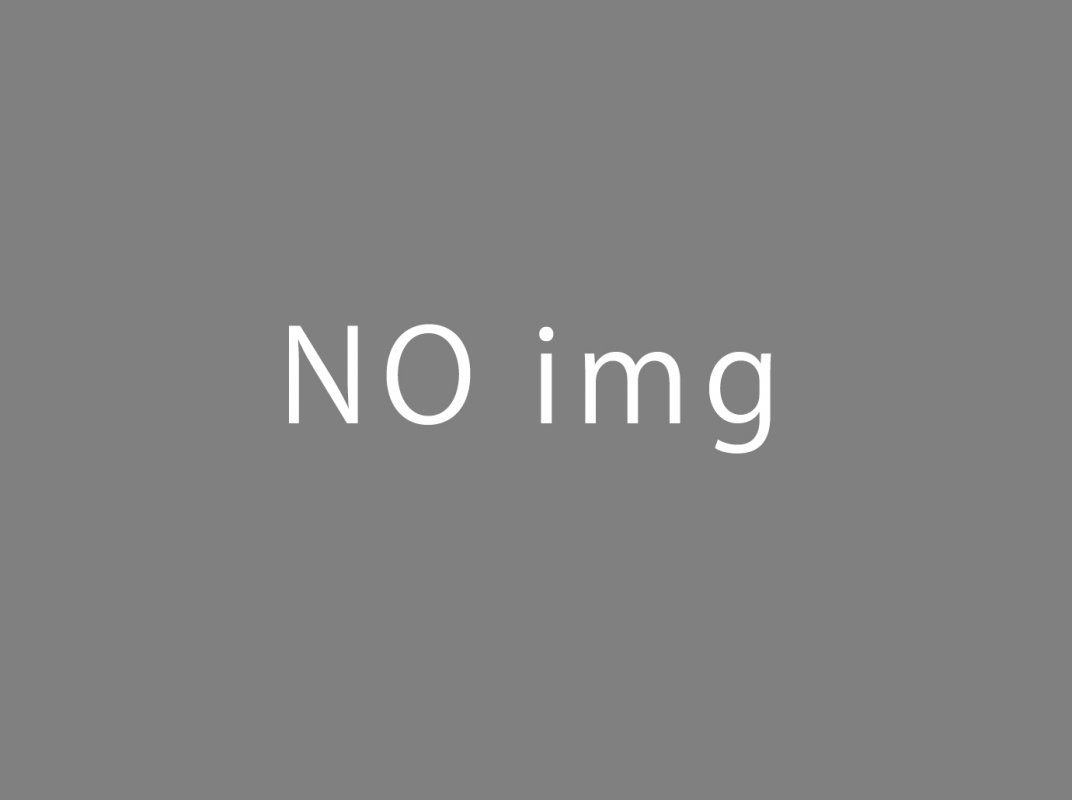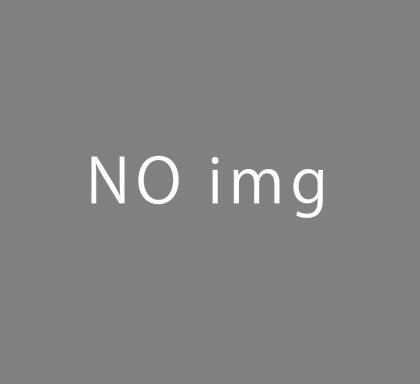+
勉強というのは…
勉強というのは、何も得点を伸ばしたり、順位を上げたりするために問題を解いたりすることではありません。
「ああ、あそこを復習しないとダメだなぁ」とか「今日は国語と、それに先生に出された課題をやっとかないとヤバいな」とか、「けっこう単語がたっまてきたから、今週末に一度単語ノートを作らなきゃ」といったように、やらなければならない、という自覚が持てるかどうか、そして、そのやるべき事柄を頭の中で大まかに構想しつつ、まいにちそれを念頭に置きながら実行できるか、という、これが勉強の実態です。つまり、自分で自分に言い聞かせ、実行することが勉強なのです。
とは言っても、習っていることがそもそも「分らない」という人もいるのでは。そういう人の場合には2タイプあって、理解が不十分な人と、習っている内容そのものの理解が出来ない人です。後者の人は、たとえ分らない内容でも、書楽に行けばわかりやすい参考書がたくさん出ていて、それらを買い込んで何度も読み返せばわかるようになりますが、そこまでやろうとする人はいないはず…、ということは「分らない」という人は、けっして頭が悪いからではなく、分ろうとしない人、今より「より善くなろう」としない人、つまり「このままじゃ、ヤバいなぁ、何とかしなくちゃ…」という気すら起こらない人である、と言えます。もっとも「人(ひと)」と言えるかどうかですが。現に、イヌネコサルは今より善く生きようとはしていませんね。ただ、飯が食いたければ食い、眠たくなれば寝るという生物的本能で生きているだけであって、人間に固有の理性的な生き方はしていません。分らなければ「分ろうとする気」が起こるかどうか、そこに大きな違いが生まれるのです。
しかし、親に言われて、または塾で厳しく指導されて、それでようやくやるようでは、まだ本物の勉強をしているとは言えません。そういうのは所詮、やらされているだけの「徒労」に過ぎず、そういうやり方で実力など身につくはずがありませんし、逆にだんだん悪くなっていきます。挙句の果てには、性格までひねくれて、暴力的反抗に出ることさえあります。強制的にやらされているばかりの、まちがった勉強をしていると、そうした間違った、虫けら同様の人間になりかねません。
だったら、正しい勉強をすればいいのです。すなわち、正しい勉強とは、先に言ったように、自分で自分を管理する理性的能力を鍛える、ということになるでしょう。分らない内容があったら、先生の所に尋ねに行くとか、本屋さんに行って参考書を買ってくるか、あるいは、問題を解いていて、「あっ、この問題、前にやっててその時も解けなかったな」と思ったら即、前の問題を机の周辺から探して、もう一度解き直し、さらに「出来なかった問題ノート」でも作って、そこに問題と模範解答をノートしておくなど、「自己管理」というのはまさにそういう勉強ができることを言います。
そんなことまで親の指示を受けたり、高い金を払ってバカな学生家庭教師を雇ったりするなんて、それこそバカげているでしょう。自分で自分の勉強をするというのは、自分で自分の服を着て身なりを整えるのとまったく同じです。親に服を着させてもらっているのですか? 親にパンツまではかせてもらっているのですか? 親に面倒見てもらわないと生きていけないのですか!勉強ができないヤツというのは、そういう低レベルの人間なんです。
しかし実際、「ああ、あそこをやっておかないとヤバいなぁ」とか、「あそこをもう1回やらないとわからなくなるなぁ」と、やるべき内容の全体の構図が見えて、その中に自分を位置づけることができることが、真の勉強のあり方だと言われても、自分で自分をコントロールできない人が問題なわけです。大半がそうかもしれません。しかしちゃんとやる子は、よく観察してみると共通して、いわば「内面の道徳的な規律性」とでも言うべき根本原理(以降、これをAとします)が、本人の中にはたらいているようなのです。でも大半の、自分で自分を維持・管理できない人、そういう人はどうすれば良いのか。
やんなきゃ、と思いつつ、しかし現状は前進するどころか、思考は停滞するわ精神は萎えてくるわ、あげくの果てに「やーめた」と放逸してしまう。しかし、そこで大事なのは、たとえば40回の単語練習を課題に出されて、40回ちゃんとやってくる子と、やって来ない子は確かにいますが、やっていない子でも、「やってきました、でもノートを忘れました」と嘯く(うそぶく)子もいれば、ちゃんと「やっていません」と言える子の、2タイプに分かれます。前者の子はやがて塾をやめていき、その辺の大手塾に行って「下」の高校へ進学し、高卒後は正社員としてはたらかず、その日暮らしをしているようです。このような子でも、「A」の原理さえ身に付ければ、立派な人に成れます。
そのためにはどうすればいいのか。それは、「たった一つのことでいいから、それをきちんとやろうとすればいい」のです。
たとえば、顔を洗う行動をとってみても、いっしょうけんめいに顔を洗う。そして水滴ひとつ残さずタオルできれいにふき取り、そのタオルもしかるべき場所にかけておく。この、たった1つの「行動」をまいにちきちんとやる。それだけでいいのです。学校のワークひとつとってみても、いつまでたってもやろうともしない人。そんな人でも、今日は1ページやってみよう、と思うだけで立派なのです。なにも始めっから「ちゃんとやれ!」とは言いません。最初はそんな軽い気持ちで始め、徐々に、生活習慣として、習ったその日に該当箇所のページの問題を解いておく、そんな生活習慣が身につけば実に優秀です。頭のよさとか悪さとか、関係ないでしょう。
今のことを、もう少し一般化して言い換えると、目の前にある1つ1つのことを外面的な「形式」の実践として行うように心がければ、やがてその「形式」が「型」となって、自分の行動原理に内面化される。こうした行動原理がひとつ、また一つと、「型」になって行けば、Aが育(はぐく)まれ、やがて先に述べた自己のコントロールができるようになるのです。本人にのみ目を向ければそういうことが言えると思いますが、そう簡単には抽象一般化出来ないかもしれません。他に考えられることは、「親」の生き様というか、親が日ごろから勉強に対して厳格な姿勢で臨まれている家庭はたしかに出来がいい、というように見えますが、一歩中に入り込むと、夫婦間の内助の功がはたらいている家庭と、父親か母親のどちらかがルーズな性格であるとか、など、外的条件はさまざまに考えられます。
子供に対してどういう「親像」が一番いいのかなんて、あるわけないでしょう。
しかし優秀な子というのは、ただ自己管理ができるだけでなくもっと自己管理を厳しくできる子です。おなじ優秀な子でも、細部に至るまで自分の弱点や、やらねばならないことが自分で見えるように「もっと勉強している」人もいれば、
言われたことはちゃんとやる程度の優秀な子など、さまざまです。将来、ひとの上に立つ子というのは中学あたりから(早ければ幼稚園ぐらいから)その片鱗を見せるものです。そういう子を見ていますと、自己管理が実に十分で、だれに・どこを指摘されなくとも己をきびしく見ることができる。だから知性が鋭く人徳もある。
こうした人間に、皆が一様になれるわけではありませんが、しかしそれでも、より善くなろうと努力するだけの価値、少なくとも、善くなろうと努力して生きる価値はあるだろうと、小生はそう考えるのです。
勉強するということ、それは義務でも強制なんかでもなく生きることそのものです。かつてギリシャの哲学者は、「より善く生きること」と言いましたが、 まさに人間である以上われわれは、より善く生きなければなりません。そのより善くの「善」=ZENとは、まさに勉強の目的であると同時に、生きる目標でもあるのです。
勉強というのは、何も得点を伸ばしたり、順位を上げたりするために問題を解いたりすることではありません。
「ああ、あそこを復習しないとダメだなぁ」とか「今日は国語と、それに先生に出された課題をやっとかないとヤバいな」とか、「けっこう単語がたっまてきたから、今週末に一度単語ノートを作らなきゃ」といったように、やらなければならない、という自覚が持てるかどうか、そして、そのやるべき事柄を頭の中で大まかに構想しつつ、まいにちそれを念頭に置きながら実行できるか、という、これが勉強の実態です。つまり、自分で自分に言い聞かせ、実行することが勉強なのです。
とは言っても、習っていることがそもそも「分らない」という人もいるのでは。そういう人の場合には2タイプあって、理解が不十分な人と、習っている内容そのものの理解が出来ない人です。後者の人は、たとえ分らない内容でも、書楽に行けばわかりやすい参考書がたくさん出ていて、それらを買い込んで何度も読み返せばわかるようになりますが、そこまでやろうとする人はいないはず…、ということは「分らない」という人は、けっして頭が悪いからではなく、分ろうとしない人、今より「より善くなろう」としない人、つまり「このままじゃ、ヤバいなぁ、何とかしなくちゃ…」という気すら起こらない人である、と言えます。もっとも「人(ひと)」と言えるかどうかですが。現に、イヌネコサルは今より善く生きようとはしていませんね。ただ、飯が食いたければ食い、眠たくなれば寝るという生物的本能で生きているだけであって、人間に固有の理性的な生き方はしていません。分らなければ「分ろうとする気」が起こるかどうか、そこに大きな違いが生まれるのです。
しかし、親に言われて、または塾で厳しく指導されて、それでようやくやるようでは、まだ本物の勉強をしているとは言えません。そういうのは所詮、やらされているだけの「徒労」に過ぎず、そういうやり方で実力など身につくはずがありませんし、逆にだんだん悪くなっていきます。挙句の果てには、性格までひねくれて、暴力的反抗に出ることさえあります。強制的にやらされているばかりの、まちがった勉強をしていると、そうした間違った、虫けら同様の人間になりかねません。
だったら、正しい勉強をすればいいのです。すなわち、正しい勉強とは、先に言ったように、自分で自分を管理する理性的能力を鍛える、ということになるでしょう。分らない内容があったら、先生の所に尋ねに行くとか、本屋さんに行って参考書を買ってくるか、あるいは、問題を解いていて、「あっ、この問題、前にやっててその時も解けなかったな」と思ったら即、前の問題を机の周辺から探して、もう一度解き直し、さらに「出来なかった問題ノート」でも作って、そこに問題と模範解答をノートしておくなど、「自己管理」というのはまさにそういう勉強ができることを言います。
そんなことまで親の指示を受けたり、高い金を払ってバカな学生家庭教師を雇ったりするなんて、それこそバカげているでしょう。自分で自分の勉強をするというのは、自分で自分の服を着て身なりを整えるのとまったく同じです。親に服を着させてもらっているのですか? 親にパンツまではかせてもらっているのですか? 親に面倒見てもらわないと生きていけないのですか!勉強ができないヤツというのは、そういう低レベルの人間なんです。
しかし実際、「ああ、あそこをやっておかないとヤバいなぁ」とか、「あそこをもう1回やらないとわからなくなるなぁ」と、やるべき内容の全体の構図が見えて、その中に自分を位置づけることができることが、真の勉強のあり方だと言われても、自分で自分をコントロールできない人が問題なわけです。大半がそうかもしれません。しかしちゃんとやる子は、よく観察してみると共通して、いわば「内面の道徳的な規律性」とでも言うべき根本原理(以降、これをAとします)が、本人の中にはたらいているようなのです。でも大半の、自分で自分を維持・管理できない人、そういう人はどうすれば良いのか。
やんなきゃ、と思いつつ、しかし現状は前進するどころか、思考は停滞するわ精神は萎えてくるわ、あげくの果てに「やーめた」と放逸してしまう。しかし、そこで大事なのは、たとえば40回の単語練習を課題に出されて、40回ちゃんとやってくる子と、やって来ない子は確かにいますが、やっていない子でも、「やってきました、でもノートを忘れました」と嘯く(うそぶく)子もいれば、ちゃんと「やっていません」と言える子の、2タイプに分かれます。前者の子はやがて塾をやめていき、その辺の大手塾に行って「下」の高校へ進学し、高卒後は正社員としてはたらかず、その日暮らしをしているようです。このような子でも、「A」の原理さえ身に付ければ、立派な人に成れます。
そのためにはどうすればいいのか。それは、「たった一つのことでいいから、それをきちんとやろうとすればいい」のです。
たとえば、顔を洗う行動をとってみても、いっしょうけんめいに顔を洗う。そして水滴ひとつ残さずタオルできれいにふき取り、そのタオルもしかるべき場所にかけておく。この、たった1つの「行動」をまいにちきちんとやる。それだけでいいのです。学校のワークひとつとってみても、いつまでたってもやろうともしない人。そんな人でも、今日は1ページやってみよう、と思うだけで立派なのです。なにも始めっから「ちゃんとやれ!」とは言いません。最初はそんな軽い気持ちで始め、徐々に、生活習慣として、習ったその日に該当箇所のページの問題を解いておく、そんな生活習慣が身につけば実に優秀です。頭のよさとか悪さとか、関係ないでしょう。
今のことを、もう少し一般化して言い換えると、目の前にある1つ1つのことを外面的な「形式」の実践として行うように心がければ、やがてその「形式」が「型」となって、自分の行動原理に内面化される。こうした行動原理がひとつ、また一つと、「型」になって行けば、Aが育(はぐく)まれ、やがて先に述べた自己のコントロールができるようになるのです。本人にのみ目を向ければそういうことが言えると思いますが、そう簡単には抽象一般化出来ないかもしれません。他に考えられることは、「親」の生き様というか、親が日ごろから勉強に対して厳格な姿勢で臨まれている家庭はたしかに出来がいい、というように見えますが、一歩中に入り込むと、夫婦間の内助の功がはたらいている家庭と、父親か母親のどちらかがルーズな性格であるとか、など、外的条件はさまざまに考えられます。
子供に対してどういう「親像」が一番いいのかなんて、あるわけないでしょう。
しかし優秀な子というのは、ただ自己管理ができるだけでなくもっと自己管理を厳しくできる子です。おなじ優秀な子でも、細部に至るまで自分の弱点や、やらねばならないことが自分で見えるように「もっと勉強している」人もいれば、
言われたことはちゃんとやる程度の優秀な子など、さまざまです。将来、ひとの上に立つ子というのは中学あたりから(早ければ幼稚園ぐらいから)その片鱗を見せるものです。そういう子を見ていますと、自己管理が実に十分で、だれに・どこを指摘されなくとも己をきびしく見ることができる。だから知性が鋭く人徳もある。
こうした人間に、皆が一様になれるわけではありませんが、しかしそれでも、より善くなろうと努力するだけの価値、少なくとも、善くなろうと努力して生きる価値はあるだろうと、小生はそう考えるのです。
勉強するということ、それは義務でも強制なんかでもなく生きることそのものです。かつてギリシャの哲学者は、「より善く生きること」と言いましたが、 まさに人間である以上われわれは、より善く生きなければなりません。そのより善くの「善」=ZENとは、まさに勉強の目的であると同時に、生きる目標でもあるのです。