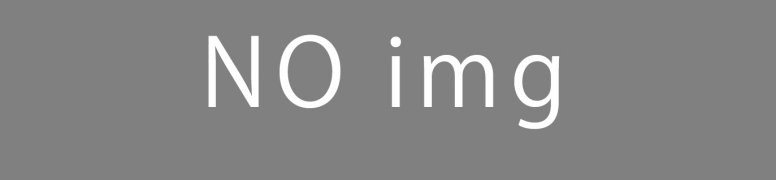ZEN説明会での質疑応答例
質疑応答内容は架空に設定したもので、こうした問いかけに対してZENはどう対応しているか、といった程度の内容として、お読みくだされば幸いです。
①「中村塾に通われている生徒さんは、みなさん優秀だとお聞きしていますが、はたしてウチの子がやって行けるのか不安です、また、貴塾はたいへん厳しい塾だともお聞きしております。うちの子は付いていけるでしょうか」(この種のご質問を、毎年いただきます!)
・たしかに優秀になるためには、ある程度の条件を満たさないといけませんが、それは弊塾の場合、出された宿題をちゃんとやってくるということですね。そんなに多くはありませんが、テキストなら2ページ程度、プリントなら1枚程度です。2時間ほどで終えられる内容です。たったこれだけのことをちゃんとやればいいのですが、それができないわけです。どうしてでしょう。大雑把に申せば、ご家庭内の道徳的規律性に問題があると思います。言われたこと、指示されたことをその場できちんと済ませる、というしつけです。
タカが中学生、頭の良し悪しなど関係ありません。弊塾には、全国で1番になる子さえいますが、本人には悪いですが、けっして優秀なわけではありません。どこが違うのか? それはただ一点、言われたことをちゃんとやるその道徳的厳格さです。そういう意味では弊塾は厳しいかもしれませんね。
いまは、宿題をやってこなくても叱らない塾に人気があり、叱ったりするとその講師は減給処分にさえなる時代です。塾も、学校の教師も、おそらく自信を持って教えてないのでしょう。自分の生きざまを生徒の前にさらけ出し問いかける、そういう、自分の人生を賭けた、存在の根底から教えきる教師でなければ、優秀な生徒は育ちません。
②「全学年の、全教科を、お一人でやっていらして大丈夫ですか?! 大丈夫ですかというのは、それ専門にやっていらっしゃる先生に比べて劣る面があるのでは、と不安ですが。」
・塾を始めた学生時代にはすでに小3から高3までの、ほぼ全教科をやっていました。しかし、私は大学の専攻が政治・経済系でしたので、理科系には薄かったため、数学や理科は高校以上の内容を極めないと、ちゃんと教えられないと感じていましたので、10年ほどかけて大学の物理化学などをやりました。また数学Ⅲなどは、難関大の入試問題を毎年解き続け、今はほぼ、どの大学の入試問題も解ける自信があります。
英語や古文はもちろん、フランス語やドイツ語、ラテン語やギリシャ語まで教える自信はあります。また、学校の先生のお作りなったプリントなどをみれば、その先生がどの程度の学識と経験をお持ちであるかまで見通せます。ですから、テスト予想問題などは簡単に作成でき、学校のテストよりも中味のある問題を数種類作成します。
このように、全学年の全教科を、いわば一教科として見渡すことができますので、どの学年で、どの単元を重点的に勉強しておけばいいかが分りますので、受験に向けて、どこの予備校よりも、効率よく勉強できるはずです。。
③「休み時間や、自習室はございますか。」
・御覧の通りの狭い、窮屈な教室です。ここ以外に教場があるわけでも、また、拡大するつもりもございません。時間割を見て頂いてもお分かりの通り、授業の入れ替わりはわずか「1分」ですから休み時間などはありません。
また、自習室を設けることに対しては否定的です。勉強は家庭内でやるもの、家庭というぬくもりの中で行うべきだからです。「うちの子は、『家では勉強できない』といいます。」というお言葉を最近よくお聞きしますが、塾の側に学習環境を期待されるのではなくて、おうちの中で、勉強する環境を作ってあげることに目を向けるべきです。
勉強は、手段ではなく、生きること自体の精神的活動ですから、家族から疎外された環境での勉強など、精神の糧(かて)になることはないでしょう。
時間割がキチキチに組まれているのは、集中して短時間に、事に処する、という姿勢が弊塾にあるからです。だらだら何時間も拘束する塾もあるようですが、そういうやり方は学習効率が低いです。
家でしっかり予習し、「さあ、これから塾に行くぞ」という心組みで臨んでいただくには、こうしたごく普通のスタイルのほうが効果があるのです。そういう考えで行っています
④「授業は、個別に見て回りながらのスタイルですか、それとも学校の授業のように全体に向けた講義授業ですか。」
・一般に数学は、答案の中身や計算の途中などを細かく見ないといけませんので個別スタイルです。一人ひとり見て回りながら、ヒントやアドバイスをして回ります。
英語は、全員で発音をしたり、英文を聞いてすぐに書き採る練習をする関係上、全体授業です。
国語の場合、最初は全体に向けて説明をしますが、記述問題の解答は一人ずつ添削をして回る個別形態です。高校生は、英文の和訳文をひとりひとり添削します。そして、実力に応じて語法や英文に関する説明を加えますので、完全な個別スタイルですが、説明が終わると今度は全員が発音します。その後、その英文を覚えて暗唱する。この場合は全体授業ですね。
このように、教科スタイルによって臨機応変に変えます。
⑤「テスト対策などは、本科授業とは別料金ですか。また対策の授業は、どのような内容で行われるのですか。」
・別料金です。1時間1500円前後で算出した講座をご案内します。
その内容は、個別に、学校別はもちろん、担任の先生の癖までを踏まえた予想問題を数種類用意したり、またその対策の勉強の仕方をアドバイスします。たとえば、中学の理科は、「学校のワーク」の解説冊子にある解説文をしっかりノートさせ、記述説明ができる背景的知識を整理するところから始めさせます。ただ単に問題を解くだけがテスト対策ではありません。高校生の古典なら、原文を見てスラスラ現代語訳ができるところまで何度も読み返したり、漢文は書き下し分を見て漢文を書く、つまり漢作文を繰り返す。こうした勉強をテスト対策時にやっておけば、何もセンター対策の勉強など必要ないのです。ふだんの勉強の仕方次第で、十分難関大学を狙える、そういう勉強の仕方をアドバイスするのが、ZENの「テスト対策授業」なのです。何度も言いますが、得点をとるための間に合わせの勉強がテスト対策ではないのです。(きちんとした勉強、しっかりした勉強のできる人のみがZENでやって行けるのです。そしてそういう人こそが、世のため人のために役立ついい仕事のできる人になれるのです。そこまでの射程を見込んだテスト対策授業です)
⑥「県立入試が記述形式に変わり、また、それにともなって北辰テストも記述形式に変ったらしいですが、こうした傾向に対して貴塾はどのような指導をなさっていますか。」
・ただ問題を解いて答え合わせをするだけでなく、学校の「ワーク」などにある 「解説」をノートすること。理科は「ワーク」解説部分、社会は教科書をノートする。国語は段落ごとに要点を書く。こうした勉強が記述問題に対する、まずは前提となる基礎力です。
・そもそも「ノートする」ことの効用は次の通りです;一度読んだ内容をアタマに入れ、今度は見ずに自力で書き、それを自己添削したあと再度書く。
これを繰り返すことで、「思考パターン」がinprinting(刷り込み)されます。単に覚えたりするよりも本質的な思考パターンが吸収され、いざ記述問題というときに、アタマのなかで既に構想が練られ、一定の表現リズムに乗って、それこそスラスラ書けるのです。同じことは単語を調べてノートに書き出すときもいえます。例えば、ジーニアス英和(G5)でwithの意味を調べたとき、付帯状況の意味説明と例文が15行にわたって書かれていますが、まずはそれを一通り読み、それをそのまま抜き出して書くのではなく、「ははぁーン、そういう意味か!」と分かった段階で、その時は辞書を見ずに、書かれていた意味と例文を書いてみるのです。書けないところはまた見直して再度書く。
たった一つの単語を調べてもそこに勉強の本質が横たわっています。そういう勉強の仕方をZENは伝授したいのです。
・こういう勉強は、人に言われてやるものではなく、自力でやって行くほかに道はありません。
記述問題が増えてきたというのは、じつは、こうした自立学習の出来る子であるかどうかを見定める形式でもあります。
⑦「高校3年生です。受験校の赤本はいつごろからやり始めるべきでしょうか。また、貴塾では入試対策としての授業は行われますか。」
・赤本は10月から使用するように勧めています。また弊塾が作成する予想問題も10月から始めます。志望する大学の2校分をすべて、次のようなやり方で進めるように指導しています。まず、時間内で解くことはせず、英語なら長文をじっくり精読する。
その際、知らないor曖昧な語法を調べてノートしつつ和訳します。この時の語法的な知識こそが受験校の要求するレベルであって、半分以上があいまいな知識であれば、その英文を全文暗唱する必要があります。実力不足だからです。数学なら、解き方が分らないとき、解説を読んでわかるようなら、今度はもっと早く解くように練習する。もし、解き方を見てもわからないようなら、「青チャート」の例題からやり直さなくてはいけません。過去問をやると言うと、すぐに何割できたかの得点を出すことと誤解されがちですが、ZENでは、過去問を一喜一憂する手段とはみなさず、過去問を用いて受験校の戦略的な勉強をします。
・また、解いているときに、「あっ、ココの個所は昔から苦手だったなぁ」と感じたら、解くのをやめて、その個所を教科書で再確認するべきなのです。それをノートに書き留めておく。そして、そのノート を試験会場に実際に持っていくと、休み時間などに、当時やった想いとともに「自信」が湧いてくるのです。そういう勉強の仕方をするのが過去問です。
⑧「受講料は銀行引き落としですか。」
・いいえ。「毎月」の初めの授業時に、「受講料袋」に封入していただき、日付印を押して当日返却いたします。この受講料袋が領収書になりまして、年末期に弊塾の顧問税理士によって収支決算を行う資料にもなりますので、紛失しないように願います。
毎月と申しますのは、弊塾の「年間スケジュール」に基づく月になります。「年間スケジュール」は別紙をご用意しております。