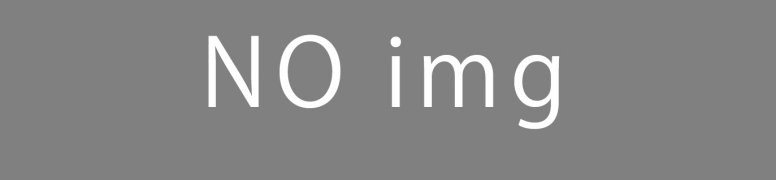中2理社講座
水曜日 7,000 円(50 分×月4回)
教材費は初回時のみ「¥2,000」です。
〈授業の流れ〉
① 理科と社会は隔週に行います
② 教科書の記述について説明し、それをノートする練習をします
③ うまくノートできるかどうかを個別に指導
④ 確認テスト⇒採点して、ノート補充
■ 理科の内容
各自の学校が今やっている単元を、学校別・個別に補習する講座です。一律に足 並みをそろえて進む授業もありますが、得手・不得手は個人差がありますから、ま ずは学校の補充が主眼です。「テキスト」の予習課題(ほとんどが復習問題で構成 されています)は解いてくる。やさしめの問題をたくさん解くことで、基礎を固めよう という狙いがあります。
たとえば「圧力」の単元は誰でも理解がスムーズに進みますが、m²をcmに換算し たり、式を言葉で説明したりするとなると、ほとんどの人が出来ない。授業ではそ の予習課題を踏まえた、類題演習でまずテスト。「圧力」に関するすべての問題を 片端から解くことで、「考え方」が身に付きます。理屈自体は簡単なのに問題とし て出されると分からなくなるのは、結局、理科の問題を解く練習量が少ないからです。最初は、その原理をあてはめれば解けるような、小学生レベルのものから始 めればよく、そうした基本問題を数多く解き進めていくうちに原理自体が飲み込め てきます。 理科は、数学とちがって、原理自体を集中的に攻める勉強が必要です。そのために、こうした授業構成にし、1題でも多くの問題を解いていただこうと考えます。
■ 分野別進度
生物
植物と動物、および細胞の3単元に分けて、単に知識の整理に終わらず、なぜ水分を吸収するのかその原理は? 血液は全身のどこで栄養分を受け取りその 栄養分とは何か、など単に知識だけではない「考える」生物問題を多く解く。
物理I
「圧力・音・光」の単元はどれも最重要であるだけでなく、またもっとも難しくなりう る単元でもあります。 入試問題(私立・国立の入試問題をふくむ)を解きながら、圧力の公式の実際的 な適用をマスターしたり、音は、速さの方程式を立てて解くとか、光は、進む方向 と像のでき方を作図する練習。そうした地道な努力を経ずして、この単元は乗り 越えられません。
物理II
電気・磁石など、数学の関数と同じく、図を見ながら式を立て計算し、それをまた 図に書き入れて答えを導き出す。そうした一連の思考プロセスをしっかり確立す ること。それが目標です。
地学
地震の計算問題、岩石の種類、地質の構造など、結果としての断片的な知識で はなく、なぜそこの地層に火成岩を多く含み、しゅう曲が見られるのか、という因果関係を考える力を身につける。
■ 社会の内容
社会は「学校の教科書」と「地図」「資料集」を中心に、どこに何が書かれているかがす ぐ分るほど、何度も読み返しながら、自分なりのノートを作るところに学習の根幹があります。
何も塾でやる必要などないわけです。しかし、自分でできないのが現実。将来に 役立つ、勉強のし「型」を身につけていただくための講座として開設します。 講座は基本的に個別指導です。
授業の中で「ノート整理」をしますが、徐々に「予習」 課題にして、授業ではその範囲の確認テストをします。そのテストの際、自分のノート以外は参照してはならず、ノートを見ても解けない場合、それはノート整理が不十分なためですから、不十分な箇所についてはその場でノート整理作業に入ります。こうして確認テストを終えた後、レベルを上げた演習に進む人もいれば、学校レベルのワ ークをみっちりやりなおす人など、進み方はバラバラです。
また、市販の参考書を1冊用意して、これをもとに自分でノート作りをすることもあります。また、授業の最初に「一 問一答」の即答テストを行います。英語の授業のように、設問を聞いたらすぐに紙に 書く即答。予習は該当単元を、教科書・参考書をもとに「ノート整理」すること。授業では、「教科書レベル」の知識の確認問題を解いてから、つぎに入試問題を解きますが、 「一問一答」の即答テストがそうした基礎知識の近道にあることを自覚してください。 要するに社会の勉強とは、教科書を念入りに読み、ノートにまとめていく作業です。 教科書のどこに何が書いてあって何は書いてない、といった明確な知識を確立させることこそが社会科の勉強で、とりわけ歴史分野は「飛鳥文化」「平安時代」など各コンテナを積み上げていくことが勉強です。
■ 分野別進度
地理I
白地図に地形を書き入れる作業から、日本の貿易にいたるまで、入試に良くでる 単元を中心にすすめる。家で作業的な勉強をやっていただき、授業では、入試問題を研究する。どういう形式で、何を問われ、記述であればどう書けばよいか、などを説明します。
地理II
各国別の地誌を一方で、他方では産業別に、たとえば中国東北部で鉄鋼業が盛 んな理由を考えたり、東南アジアの貿易の特徴を言ったり、そういう総合的な視点 に立って、地理としての論理的な考え方を身に付ける。
歴史
何度も言うように、社会は教科書を中心としたノートまとめが絶対に必要です。テスト前にあせって、間に合わせの知識で済ませようと思う人は、敗北者。学校から渡されている資料集を参照し、教科書をじっくり精読し、書かれてある内容を全て、図絵やグラフにいたるまで綿密にノートします。たとえば「貞永式目」と聞かれれば即 座に時代の全貌を語れるように、それくらい時代のイメージが語れるようにしなけれ ばならない。授業は、たとえば、「貞永式目について、その全貌を語れ」とたずねますから、スラスラと言えるようにしてくること。